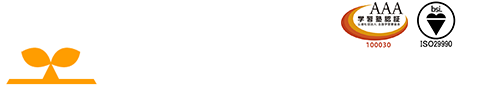お盆の時期も終わり、少しずつ日常を取り戻しつつあります。
それでも参加されるお子様はまだ暑さが続いていることもありますが元気いっぱいです。
スタッフのみんなもお子様を見習っていきます!
夏休み後半も頑張っていきましょう!
タグ: 船橋市
経営方針発表会を開催!
先日、常勤スタッフ、パート全員が集まり「経営方針発表会」を行いました。
今回のテーマは「過去を振り返り、未来を具体的に描く」。7年前の経験を土台に、これからの7年をどうつくっていくかを全員で共有しました。

7年前から未来へ
青沼塾長からは、経営理念やこれまでの歩み、組織の役割について話がありました。
2018年当時の大変な時期を乗り越えてきたからこそ、今の私たちがあります。
そして7年後には「売上・利益の拡大」「地域で最も働きたい企業No.1」「学校法人や福祉法人の取得」「新規事業展開」といった明るい未来像が示されました。

今期の合言葉は「変化を楽しむ」
小泉統括マネージャーからは、今期の経営計画について発表がありました。
伸栄学習会は2歳から60代まで、幅広い世代の方を支援しています。
それぞれの事業はつながっており、相互に力を発揮できるのが大きな強みです。今年はグループホームやカフェといった新しい事業も始まりました。合言葉は「変化を楽しむ」。スタッフ一人ひとりが具体的なアクションを起こし、支援の質・指導技術・利用者数など、すべての面で“地域ナンバーワン”をめざします。

各事業からの発表
-
就労
慣れた環境で安心して働ける場を提供し、利用者さんがステップアップできる事業所にしていきます。イベント販売や冊子づくりで利用者さんの思いを発信していきます。新しく「就労選択支援」も始まります。 -
訪問看護
子育てや進学、就職をきっかけに悩む方に寄り添っていきます。教育・デイ・就労部門とも連携できる訪看は他にない。9月から訪問件数を増やし、さらに多くの方にサービスを届けていきます。 -
松陰高等学校
不登校経験のある生徒に合わせて学習を設計できることが強み。大学進学率85%を誇り、修学旅行やボランティア活動も大切にしています。ゴールは高卒資格だけでなく、その先の未来につなげることです。 -
塾
ターゲット層を明確にしました。当塾の強みである「徹底した生徒管理」をもっと実感してもらう取り組みを。保護者の信頼を得ながら、専門塾も合わせて集客を強化していきます。 -
放課後等デイサービス
学力を伸ばす教室運営、特性に応じた学習支援、学ぶ楽しさを伝える取り組み を展開。データ活用や助け合いの仕組みも整えていきます。 -
グループホーム
「全部やってあげる」というスタンスではなく、洗濯の方法を教える、など自分でできることを増やす支援をしていきます。専門スタッフと連携し、安心した自立を目指します。

 これからの一歩
これからの一歩
今回の発表会を通して、全員が未来に向けてのビジョンを共有できました。私たちは「変化を楽しむ」を胸に、地域にとって一番信頼され、安心して選ばれる存在を目指してまいります。
富士見教室の高校生、テコンドー全国大会で活躍!
今回は、富士見教室に通う高校生の活躍をご紹介します。
この生徒はテコンドーの大会で優秀な成績を収めており、最近では「全日本大会 2位」「オープン大会 2位」などの実績があります。
さらに、オリンピックアスリート強化支援事業の強化選手にも選出されました。
伸栄学習会では、この生徒を応援するために、道着に「伸栄学習会」のロゴをプリントし、大会で着用していただいています。

今後もさらなる飛躍を期待し、応援を続けていきます!
イベント卓球大会開催!その②(入船教室)
8月15日(金)、バルトラール総合体育館で、2年連続となる卓球大会を開催しました。今回は共同開催のため、富士見教室から2名が参加してくれました。


当初、参加者が少なかったものの、、徐々に人数が増えていきました。
本番では、卓球を楽しみにする雰囲気が広がり、今年は大会開始前から盛り上がりを感じました。

参加者は親子だけでなく、父親や母親、おばあさんと一緒に来てくださる方々もおり、本当に楽しい時間を共有することができました。


練習のみの利用者はおらず、全員が参加できるトーナメント方式の試合が実現できたことは素晴らしかったと思います。2時間の時間はあっという間に過ぎ、全員が楽しんで笑顔を見せてくれました。
お盆明け、元気いっぱいの子ども達
8月もお盆が終わり、夏休みも折り返しとなりました。
お盆の期間には家族で帰省した子ども達も多く、充実した時間を過ごして戻ってきた姿が続々と教室に見られます。日に焼けてすっかり印象が変わった子もいて、思わず驚かされました。言葉にしなくても、その表情や様子から楽しい時間を過ごしたことが伝わってきます。
そんな子ども達の姿を、学校の先生や友達よりも少し早く知ることができるのは、夏休みならではの密かな特権かもしれません。たくさんの話を聞かせてもらい、スタッフ一同すっかり“お腹いっぱい”になりました。
特性やその子に合う学び方理解できる「NOCC教育検査」とは?
こんにちは。市川市の放課後等デイサービス「伸栄学習会 末広教室」です。
伸栄学習会では、子どもたち一人ひとりの特性や学び方の違いを丁寧に理解するために、NOCC検査を導入しています。
NOCC検査とは、視覚・聴覚・空間認知・記憶など、子どもの「認知のかたより」や「つまずきやすいポイント」を見つけることができる検査です。
例えば、「聞いて覚えるのが苦手」「書くことに時間がかかる」「空間認知が弱い」などの特性は、日常の学習場面にも大きく影響します。
NOCC検査を通じて、こうした課題の“見えにくい原因”を可視化し、一人ひとりに合わせた支援計画や学習方法の工夫へとつなげています。
「どうしてこの教科だけ苦手なの?」「集中できないのはなぜ?」といった疑問をお持ちの保護者の方にも、検査結果をもとにわかりやすくご説明いたします。
ご希望の方には個別面談も行っております。
ぜひ伸栄学習会 末広教室にご相談ください。
イベント卓球大会開催!(入船教室)
8月15日バルドラール浦安アリーナにて卓球大会を開催しました。
今年は富士見教室からの参加も含め、多くの生徒さんや保護者の方が参加してくださいました。
松陰高校からは3名の生徒さんがボランティアとしてお手伝いをしてくださいました。
優勝は二年連続K君でした。
終わった後、教室にてミニ表彰式を行いました。
みんなに祝ってもらったK君はお顔一杯の笑顔を見せてくれました。
社会性が身につく!SST教室参加者大募集!(富士見教室)
富士見教室では毎週土曜日の17:00~ディスカッションのSST教室を行っています。
様々なテーマでSST(ソーシャルスキルトレーニング)を行っています。
先日は「1分間スピーチをしよう」というテーマで行いました。
参加した児童・生徒が発表した内容の一例として、「昨日、お友達と遊んで、虫取りをしたり、児童館へ行ったこと」、「今日お父さんとアイスを食べに行って、美味しかったこと」、「将来、生物の研究者になりたいこと」などについて発表しました。
その他にもテーマを決めて、毎回ソーシャルスキルを身につけていっています。
参加するメンバーは現在大募集中!ですので、興味がありましたらお問い合わせください!
色綿を使ったキャラクター作り
Oさんは、綿をたくみに使って個性豊かなキャラクターを作り上げることが得意です。
今回は、かわいらしい犬のチワワや、
人気キャラクターのカービィを上手に作り上げました。


ふんわりとした質感の中に、
思わず笑みがこぼれるような愛くるしい表情が表現されており、
見る人の心を和ませてくれます。
これからも、たくさんの楽しい作品を作って下さい。
楽しみにしています。
英語の日!
先日、英語の学習支援を行いました。
英語に初めて挑戦する子もいて、少し緊張しながらも、テキストと動画を使ってヒアリングを中心に学習しました。
ネイティブの発音に耳を傾け、単語を繰り返し発音するうちに、だんだんと笑顔が見られるように。
分からないことにも前向きに取り組む姿が印象的でした。英語の音やリズムに慣れながら、楽しく学べる時間となりました。