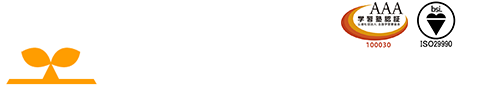7月に入り、連日たくさんの方にお越しいただき、教室は満員となる日が続いております。本当にありがとうございます。
「どうしてそんなに満員なの?」
そんな嬉しい声をいただくこともあります。今日は少し、その理由をお伝えさせてください。
私たちは、お子さまとの出会いを「ただの通塾」ではなく、“特別なご縁”と考えています。
一人ひとりが教室の中で自信をもち、のびのびと輝けるよう、心をこめて向き合っています。
✨ 授業の特徴は、「1分間指導」と「関所指導」
お子さまがつまずきやすいポイントをピンポイントで指導し、「わかった!」「できた!」という成功体験を積み重ねていきます。
これが大きな自信に繋がっていくのです。
✨ 先取り学習で「わかる!」を先に
学校より一歩先を学ぶことで、「あ、これ聞いたことある!」という安心感が。
この積み重ねが、やる気と笑顔に変わります。
✨ 学びの幅も広がっています
・デジソロ(デジタルそろばん)
・タイピング練習
・プログラミング(スクラッチ)
・ビジョントレーニング(視覚認知の課題サポート)
・SST(ソーシャル・スキルトレーニング)
「ここなら、自分らしくいられる」——
そう感じてくれるお子さまが増え、週3〜5日の通塾を希望されるご家庭も多くなっています。
このようなつながりが、地域への貢献にもつながっていることを、大変うれしく思っております。
これからも、ひとつひとつの出会いを大切に。
お子さまとご家庭を、全力でサポートしてまいります!