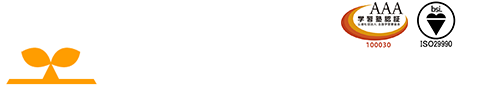手先が不器用。
漢字を書くのがしんどい。
なかなか覚えられない。
漢字を書くには、
意味の記憶、視覚の記憶、運動の記憶、運動を制御する力、運動を設計する力(運動企画)等々が関係しています。
そのうち、運動企画とは、
漢字を書く際に、
「こう動かして、次はどこに書いて・・・」等、
動かしかたを設計する力です。
しかし不器用だと、
書くことに大きな力を注がざるをえず、
運動企画にまわす余裕が少なくなってしまいます。
設計のイメージがないままに、行き当たりばったりだと、
覚えることはできても、「考えなくてもスラスラ書ける」ようになるまで大変な労力が求められます。
しかし、書くのが苦手であれば、くり返し書くのが一層の苦行。
覚えられないわけではないけど、それを乗りこえて覚えるまでに、継続できるかというのがつらいところです。
そこで、
『まんがとゴロで楽しく覚えて忘れない 小学漢字1026』
という本が役に立っています。
友という字であれば
「ナヌっと友がふりむく」というように、漢字を分解してゴロで覚えるというものです。
友は10画の漢字です。
10回も「次はどう書く?」と判断が必要です。
でもカタカナの「ナ」と「ヌ」なら、
判断は2回だけ。ぐっと楽になります。
負荷の量を減らせば、余裕ができ、
漢字の形を覚えたり、意味を理解したりすることに
力を回すことができます。
なんとか乗りこえられるように頑張っていこう!