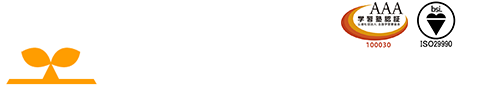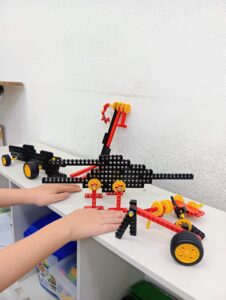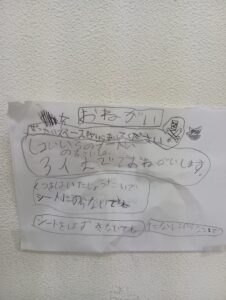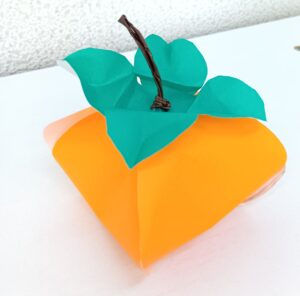「今日も霧吹きやる?」
シュッシュッシュッ・・・
小さいボトルですが、がんばって霧吹きのボトル1本分をだしきります
霧吹きを握る運動で、手指のトレーニング。
適切な筆圧でペンをコントロールするには、一定の握力が必要とされています。
握力が不足すると、力を入れすぎて書いたり、逆に弱すぎて薄い字になったりします。
ボールを握る、ハンドグリッパーなど色々やりましたが、
霧吹きが淘汰されて残りました。
水が目に見えて減っていくこと、
握ったときの「しゅぅーーっ」という気持ちよさがあるからですかね・・・?
「次は洗濯ばさみね。」
親指と人差し指で「カチ、カチ、カチ・・・」
洗濯ばさみ で 指先の精密な力や独立性を訓練します
特に親指と人差し指を独立して動かす能力は、書字に直結するスキルです。
土台となるトレーニングとあわせて、実際の書字練習も。
「じゃあ、次は迷路やってみようか」
楽しく継続しながら、無理なく書く力を育てていきましょう!