先日、数学(算数)検定が行われました。
数学検定の5級以上は一次試験と二次試験があり、この二つの試験を同じ日に実施します。
検定当日は、この時期にもかかわらず真夏のような暑さで、教室に来るだけでも大変でした。
さらに、その日に二つの試験に挑んだ子どもたちは、本当に大変な一日だったと思います。
そんな大変な一日を頑張ったのですから、ぜひ合格というご褒美を手にしてほしいと願っています。
先日、数学(算数)検定が行われました。
数学検定の5級以上は一次試験と二次試験があり、この二つの試験を同じ日に実施します。
検定当日は、この時期にもかかわらず真夏のような暑さで、教室に来るだけでも大変でした。
さらに、その日に二つの試験に挑んだ子どもたちは、本当に大変な一日だったと思います。
そんな大変な一日を頑張ったのですから、ぜひ合格というご褒美を手にしてほしいと願っています。
妙典教室では、中学生の定期テストが返却された後、解き直しをしています。
学校にもよりますが、テスト終わりに正解を先生が生徒たちに提示してくれても、解説までの時間を設けていないそうです。
テストで間違ったまま、何もしなければ、間違った解き方がインプットされたままで、もしかすると高校受験本番でも…となってしまいます。
復習や解き直しを生徒たちは嫌がりますが、実は、一番大切な学習だと私たちは伝え、一緒に取り組んでおります
Yさんはパズルが大好きです。
今回は平面の箱詰めパズルに挑戦しました。
最初に三角形や正方形・平行四辺形のビースを箱から出してばらばらにします。

その後組合せを考えて箱の中にもう一度戻すパズルです。
簡単なようでいて意外と難しく頭脳の良いトレーニングになります。


Yさんは楽しみながらいろいろ考えて全部のピースをきれいに元に戻すことができました。
すばらしかったです。
これからもいろいろなパズルに挑戦して下さい。
富士見教室にて、科学実験・科学工作イベントとして「人工イクラ作り」を行います。
日時は7月21日(月、祝日・海の日)16:00~17:00です。
興味がある方のご参加お待ちしております。
他の教室からの参加も大歓迎です!
今後もまた行う予定ですので、今回ご都合が合わない方も次回以降興味があればご参加ください。
もしかすると他の教室でも行うかもしれません!?
今回は、私たちの事業所で行っている SST(ソーシャルスキルトレーニング) の活動についてご紹介します。
SSTとは、子どもたちが「人との関わり方」や「自分の気持ちの伝え方」など、社会で生きていく上で必要なスキルを学ぶ時間です。
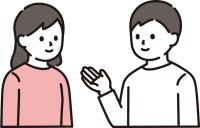
■ 今日のSSTのテーマ:「お願いの仕方を練習しよう!」
今日の活動では、「○○してほしい」と伝えたいとき、どんなふうに言えば相手が気持ちよく聞いてくれるかを、ロールプレイを通して学びました。
活動の流れはこんな感じ:
絵カードを見ながら、「お願い」の例を紹介
「パソコンをやりたい」「順番を代わってほしい」など、よくある場面を想定しました。
スタッフとロールプレイ
「ダメって言われたらどうする?」「ほかにどう言えばよかったかな?」など、やりとりを実際にやってみました。
ふりかえりタイム
「言えた!」「ちょっと恥ずかしかったけど頑張った」など、それぞれの子どもが感じたことを共有しました。
■ 子どもたちの反応
最初は恥ずかしそうにしていた子も、友だちのやりとりを見るうちに、「やってみたい!」と前に出てきてくれました。
ある子は、普段はスタッフに頼ることが多いのですが、今日は自分で友だちに声をかけることが出来て、大きな成長を感じました。
■ SSTで大切にしていること
・無理にやらせない
・小さな「できた!」を一緒に喜ぶ
・成功体験を積み重ねる
子どもたちが「人と関わるって楽しい」「伝えていいんだ」と感じられるように、安心できる関係の中で進めています。
■ 保護者の方へ
SSTの内容は、おうちでも実践できます!
「貸してって言えたね、すごいね」「今の言い方、やさしかったね」と、ちょっとした場面で声をかけてもらえると、子どもたちの自信につながります。
最後に
日々のSSTの積み重ねが、子どもたちの未来につながると信じて、これからも丁寧に関わっていきます。
今回の研修では、改めて「私たちの事業所が目指す支援とは何か?」を全員で共有し、支援の質の向上とチーム力の強化を図ることを目的としました。
まずは、代表から私たちの事業所の目指す姿について話があり、各事業のコンセプトについて講和がありました。
日々の業務に追われる中でも、原点に立ち返り、私たちの支援が誰のためにあるのかを確認する大切な時間となりました。
また、後半にはグループワークも実施。
「伸栄学習会のコンセプトを考える」をテーマに、少人数に分かれて話し合いました。
それぞれの経験や思いを交えながら意見を出し合い、チームとしての一体感もより強くなったように感じます。

今回の研修を通じて、スタッフ一人ひとりが同じ方向を向いて支援に取り組んでいくための、良い機会になりました。
今後もこうした時間を大切にしながら、よりよい支援を提供できるよう努めてまいります。
今月の壁面装飾はあじさいです。
花や葉に好きなように模様を描いたり、シールを貼ったり、様々なあじさいが教室の壁に咲きました。
勉強の休憩で創作に取り組み、良いリフレッシュになりました。

梅雨の時期らしくない天気が続いていますが、夏にむけて準備していけたらと思います。
6月21日は「夏至」。
一年でいちばん昼が長くなる日でした。
日差しが強くなり、少しずつ夏の気配も感じられるようになってきました。
この時期は、まだ体が暑さに慣れていないこともあり、熱中症には特に注意が必要です。
外で遊ぶときはもちろん、室内でも油断せず、水分補給やこまめな休憩を心がけましょう。
「のどがかわく前に飲む」「無理せず涼しく過ごす」——そんな小さな工夫が、元気な毎日につながります。
これからますます暑くなっていきます。お子さんも大人の方も、体調に気をつけながら、楽しい夏を迎えましょう。
昨年度に続き、今年度も千葉東高校ジャグリング同好会の皆さん(高1~高2のメンバーと先生)が来てくださいました。今回で3回目となり、高校生の皆さんとの間にとても良い関係が築かれてきているのを感じます。

今回は、相之川から親子1組、富士見からお子さん1名、入船からは親子2組、そして松陰からは1名のボランティア参加があり、子どもだけでも12名が参加してくれました。そのほかにも、保護者やご兄弟の方々のご参加もあり、にぎやかな時間となりました。



時間は1時間足らずと短いものでしたが、子どもたちはそれぞれが興味を持ったジャグリングに積極的に取り組んでいました。高校生たちに教わりながらも、しっかりとコミュニケーションを取り、楽しく充実した時間を過ごしている様子が印象的でした。

また、他の教室から参加された保護者の方が「こういったイベントもされているんですね」と感動されていたのがとても嬉しかったです。活動の終わりには、「できるようになった!」と子どもたちが達成感を持って笑顔で終える姿が見られました。
今後も機会があれば、ぜひ千葉東高校ジャグリング同好会の皆さんに来ていただきたいと思っています。
天文学オタクのお友達の投稿で、今日の夏至がとても珍しいと知りました。✨🌙🌞
調べたところ…
2025年6月21日の夏至は「極めて珍しい」。
それは数千年に一度の奇跡。
それは日本の東京での「夏至点(太陽が黄道上で最も北に達する瞬間)」と「太陽の南中(その日、太陽が空で最も高くなる瞬間)」が、ほぼ完全に一致するためです。
通常、夏至点と南中時刻は数分〜数十分ずれるのが普通。
ですが、2025年は6月21日11時42分に、東京でこの2つの現象が同時に起こります。
これは地球の公転・自転、標準時の設定など多くの条件が重ならないと実現せず、「数百〜数千年に一度」と言われるほど稀です。
この瞬間、天文学的にも象徴的にも「時空の奇跡」と呼ばれる現象となっています。
天文学好きなお子様には
ワクワクなお話ですね。
🌏✨