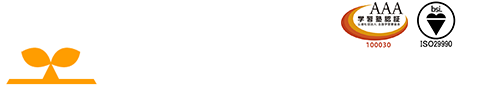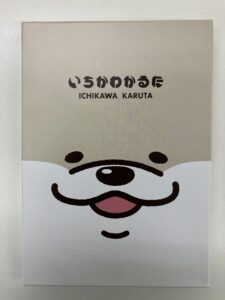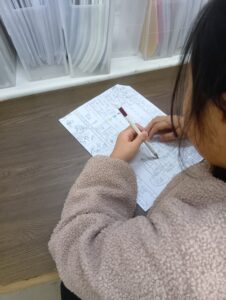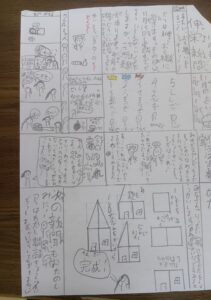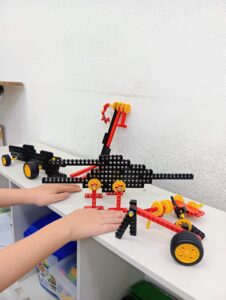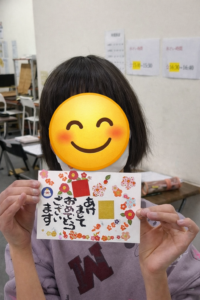授業の合間の休み時間、教室からはいつも楽しそうな声が聞こえてきます。
最近、末広教室の生徒たちが夢中になっているのが「ブロックス」です!
🧩 休み時間の真剣勝負!
生徒たちが畳の上でリラックスしながらも、真剣にブロックスを楽しんでいる様子です。
「どこに置こうかな…?」「そこ置けちゃうの!?」と、学年を超えて盛り上がっています。
ブロックスは、自分の色のタイルを角と角がつながるように置いていく陣取りゲーム。
ルールはシンプルですが、実はとっても奥が深いんです!
💡 遊びは「最高の脳トレ」
一見ただの遊びに見えますが、実はこれ、算数や数学で大切な能力を育てる絶好のチャンスでもあります。
図形認識力:さまざまな形のピースをどこにはめるか考える。
先を読む力:相手の動きを予測して、自分の陣地を広げる戦略を立てる。
集中力:限られたスペースの中で、最後まで諦めずに考える。
「勉強しなさい!」と言われると構えてしまう子も、ゲームなら夢中で頭をフル回転させています。
「次はどう動こう?」と自ら考える楽しさは、勉強もゲームも同じです。
伸栄学習会は、子どもたちの「やってみたい」「勝ちたい(解きたい)」というポジティブなエネルギーを、日々の学習意欲へと繋げていけるような場所でありたいと考えています。