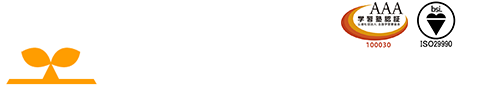心は 「ことば」でできている
私たちの身体は食べ物でできています。
安心安全な食材、質の良い栄養は健康な身体づくりの土台となります。
では、目に見えない心は何でできているのでしょうか。
それは乳幼児期からの大人との質の良い関わりです。
乳幼児期に周囲の大人がどう接するかで、 その後の人生が決まるといわれるほど、環境要因は子どもの情緒面での発達に大きな影響をもたらします。
中でも言語環境の研究では、親や保育者の「ことばがけ」が子どもの脳をつくるとされています。
子どもに肯定的で豊かなことばをたくさんかけることが、
安定した心の発達につながるということです。
子どもは常に大人に見てほしいという欲求があります。 自分の行動
を見てもらい、 応答してもらい、共感することばをかけてもらい安心を感じると、子どもはもっとコミュニケーシ
ョンを取りたいという気持ちになります。
こうした相互作用の繰り返しが言語発達、知性や社会性の発達、情緒発達などの手助けとなるのです。
親や先生は子どもが安心する共感ことばをどれだけかけているでしょうか。
本来、子どもは電子音よりも自然な人の声が好きです。
だから子どもたちは人の声の温もりが伝わる子守唄やわらべ歌が大好きで何度も繰り返し聞きたがるのです。
人の声を聞くことで人のことばを認識理解する脳の分野が発達します。
赤ちゃんにとって電子音は不自然で刺激が強すぎるため学習効果が得られません。
人類 700万年の歴史の中で電子機器が現れたのはごく最近のことですから、
日常的なスクリーン映像は子どもの脳にかなりの負担がかかっていると考えられます。
人の声にはトーンがあり、喜怒哀楽やその時々に込められた想いは声や表情を通して感じ取ることができま
す。 心地の良い安心ことばや肯定ことばを耳にする機会が多い子どもは、
自分の価値を知り、心も豊かに日常を過ごすことができるでしょう。
逆に大人の怒り声や否定ことばを日常的に耳にしている子どもたちの心はどうでしょう。
不快な言語環境では脳が過敏に反応し不安になったり、常に周囲を気にしたり、自分の価値を確認する指標がなく心が寂しくなったり。
ことばは言霊。
ことば一つで幸せな気持ちになることもあれば、ことばによある誹謗中傷で命を落とすことさえもあるのですから、ことばが持つエネルギーはとてつもなく大きいです。
目には見えない子どもの心を豊かに育むために、日常的にすてきなことばをたくさんかけてあげたいですね。